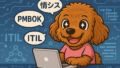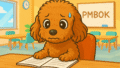ITILとは?基礎知識と活用事例を解説

こんにちは、あんずです♪ 今日は「ITIL」というITサービス運用の“教科書”について、一緒に学んでいきましょう!
ITILは何の略語?簡単に日本語で説明すると・・・
ITIL(Information Technology Infrastructure Library)は、ITサービスマネジメントのベストプラクティスをまとめたフレームワークです。英国政府が1980年代後半に開発し、運用・サポート・改善までのプロセスを体系化しました。
【補足】直訳すると「ITインフラストラクチャの図書館」。複数のガイドラインや手順書を体系的にまとめたものを指します。
概要
ITILは、ITサービスの計画・設計・移行・運用・継続的改善といったライフサイクル全体をカバーします。その目的は、ITサービスの品質向上、顧客満足度の向上、コスト削減、そして業務効率化です。
策定団体は英国政府商務庁(OGC:Office of Government Commerce)で、その後AXELOSが管理を引き継ぎ、現在では世界的に広く採用されています。
特徴
- サービスライフサイクル全体をカバー:計画から改善まで一貫した流れ
- ベストプラクティスの集大成:多数の事例をもとに体系化
- 柔軟な適用が可能:全てを導入する必要はなく、必要な部分だけ採用できる
- 他フレームワークと親和性が高い:PMBOK、COBITなどと組み合わせやすい
【補足】ITILは“守るべき規格”ではなく“参考にする手引き”です。
活用事例
- 大手SIerの運用センターでのオペレーション標準化
- ITアウトソーシング企業におけるサービス品質保証
- 金融機関のシステム障害対応プロセス改善
- 大規模クラウドサービスの運用管理最適化
【補足】業種や規模を問わず、ITサービスを提供する現場で幅広く利用可能です。
メリット・デメリット
メリット
- 品質の安定化と向上
- 作業手順の標準化による効率化
- 顧客満足度の向上
- ナレッジ共有の促進
デメリット
- 導入コストや教育コストがかかる
- 過剰なプロセス化による柔軟性の低下
- 現場に馴染むまでに時間がかかる場合がある
他フレームワークとの関係
ITILはPMBOKやCOBITと補完的な関係にあります。例えば、PMBOKのプロジェクトマネジメント手法にITILの運用プロセスを組み合わせることで、計画から運用までの一貫した管理が可能になります。
【補足】COBITはITガバナンス寄り、ITILは運用寄りと覚えると理解しやすいです。
まとめ
ITILは、ITサービス運用の質を底上げするためのベストプラクティス集です。すべてを取り入れる必要はなく、現場に合わせて柔軟に活用するのがポイントです。

ITILは、情報システムの運用の“教科書”みたいな存在だよ! 次回も「IT関連知的フレームワーク」を一緒に見ていこうね♪